前回は、物件調査のあとのゴタゴタについて書きました。約1ヶ月の喧騒のあと、いよいよ競落人(最高価買受申出人)が登場します。この方は新しい大家さんになる方ですので、今後のあなたの住まいに大きな影響を与えることになります。対応を間違えないように注意点を見ていきましょう。
競落人って何?家賃は誰に払うの?

入札期間が済んで約1週間後に開札期日があります。開札期日とは、裁判所で入札された札を開封し、一番高い金額を付けた人に売却することを決める手続きのことです。この一番高い金額を付けた人を、俗に「競落人(けいらくにん)」といいます。もっともこの段階ではまだ「最高価買受申出人(さいこうか/かいうけ/もうしでにん)」です。
競売情報も開札期日も一般にも公開されているので、心配な方は、事前に競売情報を見て、あなたの自宅の競売事件の番号と開札期日を調べておくと、誰が落札したか見に行くことが出来ます。
競売情報は、裁判所が運営する情報サイト(不動産競売物件情報サイトBIT)で公開されていますので、期間中は裁判所に行かなくても誰でも閲覧できます。また、落札情報は短期間でしたらインターネットで公開している業者さんもありますので、裁判所に行かなくても誰が落札したかは調べることも出来ます。(BITでは落札者が法人か、個人かくらいしか公開されていません。)
ただ、注意して頂きたいのは、一番高い金額の札を入れたからといって、その方が本当に新しい所有者(大家さん)になるかどうかは分からないと言うことです。
競落人が新しい大家さんじゃないの?

競売で一番高い金額を入れた人が新しい所有者になれば、原則として家賃は新しい大家さんに払うことになります。ただ、これからしばらくは、権利関係が大きく動くタイミングですので、とても複雑です。家賃を誰に払うべきなのか、じっくり考えて行動しましょう。中には、ゴタゴタの隙を突いて騙してやろうとする人も出てきますので、手紙や連絡は鵜呑みにせず、でも放置もせずに対応していきましょう。
まずは大原則から見てみましょう。
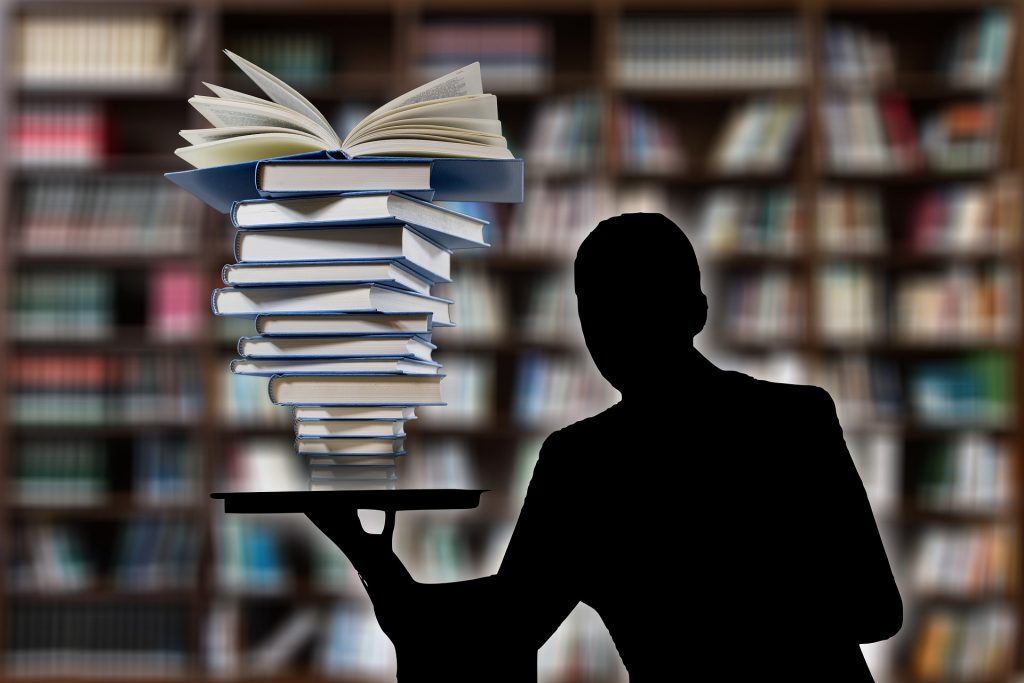
開札期日で一番高い金額を付けていた人が、最高価買受申出人になることは先ほどの書きました。ただ、読んで字のごとく「一番高い金額(最高価)で『買います』(買受)と言った人(申出人)」でしかありません。
裁判所は、この方宛に「売却許可決定」というものを発令しますが、「あなたに売ります」と決めたに過ぎません。裁判所は同時に「だから1ヶ月以内に売却代金を振り込みなさい」と決定します。そして、その決められた期限内に代金を支払って(「代金納付」と言います。)はじめて買受人=新所有者になるのです。つまり、この時はじめて大家さんになるのです。
代金が裁判所に支払われるまでは、大家さん=あなたの物件の所有者は、あくまでも賃貸借契約をした大家さんです。ちゃんと代金が支払われたかどうかは、あなたの借りている物件の登記簿を見れば分かります。支払いが済めば、裁判所が所有権移転登記手続きを嘱託するからです。
ついに新しい大家さんと話し合い?

おそらく開札期日が済んだ頃に、買受人を名乗る方が連絡をしてくるでしょう。この方が本物かどうか、既に代金納付が済んでいるのか、この時点ではまったく分かりません。そこで、こんな風に聞いてみて下さい。
「売却許可決定の写しを見せて貰えませんか。代金納付はいつ頃される予定ですか。」
たいていの業者さんは一瞬ひるむと思います。「こいつ、プロかも知れない」
最高価買受申出人になった業者さん(最近は一般の方もいらっしゃいますが)は、十中八九、代金を支払う前に接触を図ってきます。なぜ?もちろん、今お住まいのあなたが、今後、家賃を払ってくれるのか、立ち退きを考えているのか、どちらも拒否して居座り続ける問題のある人なのか、を見極めるためにです。
最悪の場合は、代金納付せず、入札時に納めた証拠金を放棄しても、リスクから逃れようとします。入札した業者さんも不安でいっぱいなのです。
ですので、もしこのまま今のご自宅に住み続けたいのであれば、最大限の注意は払いつつ紳士的に対応して下さい。代金の支払いが済めばその方が新しい大家さんになる方ですから。
結局、新しい大家さんとは、どういう関係になるの?

売却許可決定の写しと所有権移転済みの登記簿の写しを貰えれば、ほぼその方が新しい大家さんと考えて問題ありません。今後の契約について話し合う必要があります。
新しい大家さんは、あなたに引き続き住んで(家賃を支払って)欲しいと考えているのか、出て行って欲しい、と考えているのか。まずはその話をしてくると思います。
でもここにも複雑な契約関係の闇が潜んでいます・・・。長くなったので続きは次回に詳しく書きますね!
今回は、競売になった借りている部屋の開札期日後について書いてみました。
このあたりからどんどん複雑になっていきますが、出来るだけ分かりやすく書くように努力しますので、がんばって読んで下さいね。
結局、私はどうすれば良いの!?という方は専門家(弁護士)に相談してみましょう。きっと詳しく教えてくれますよ。

