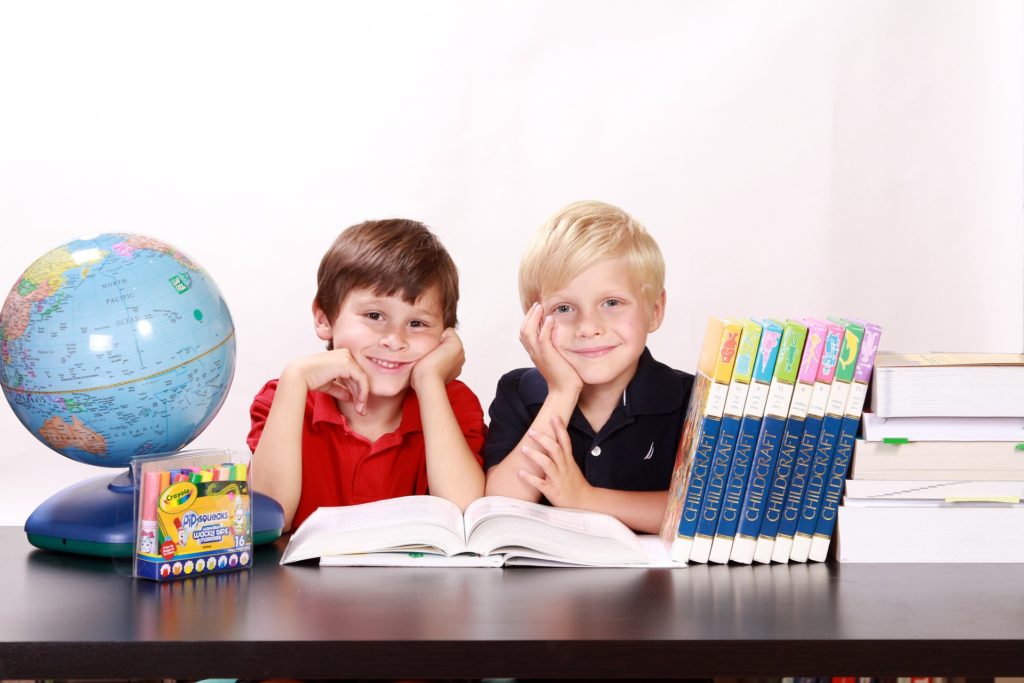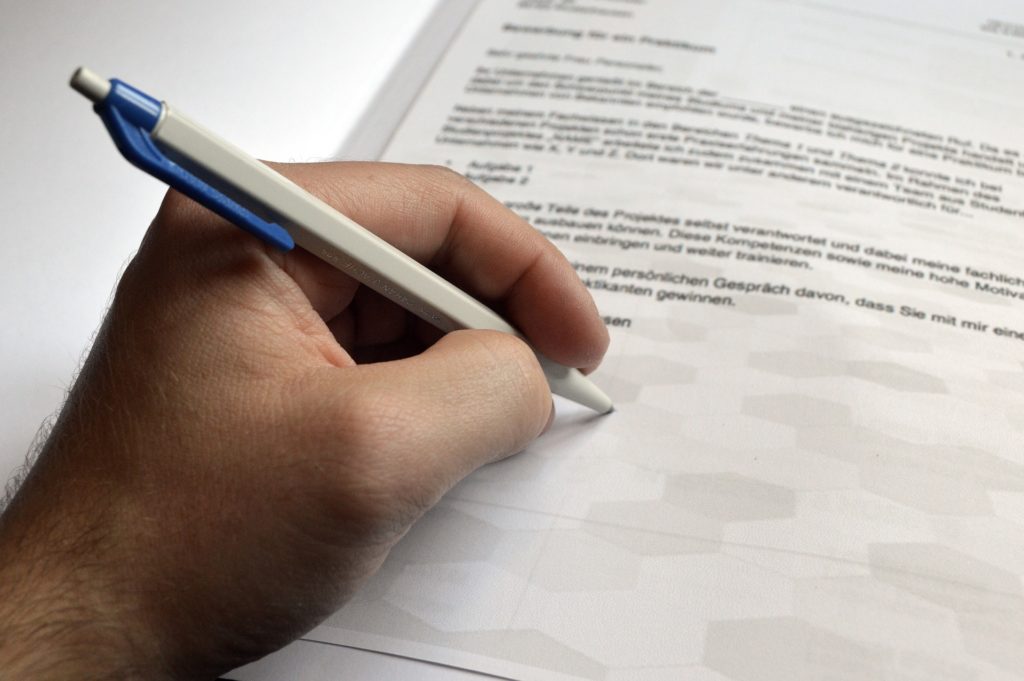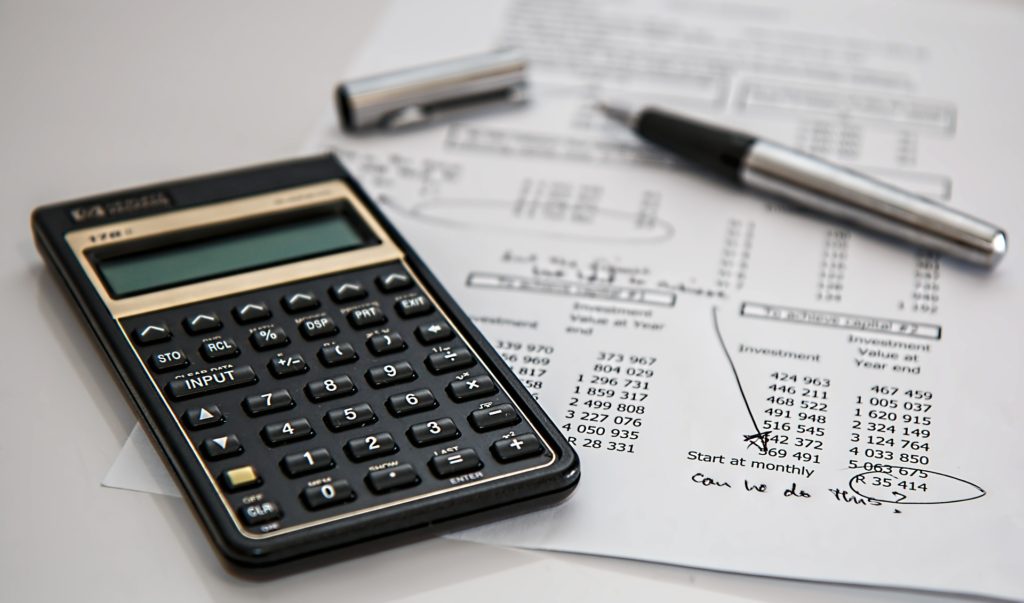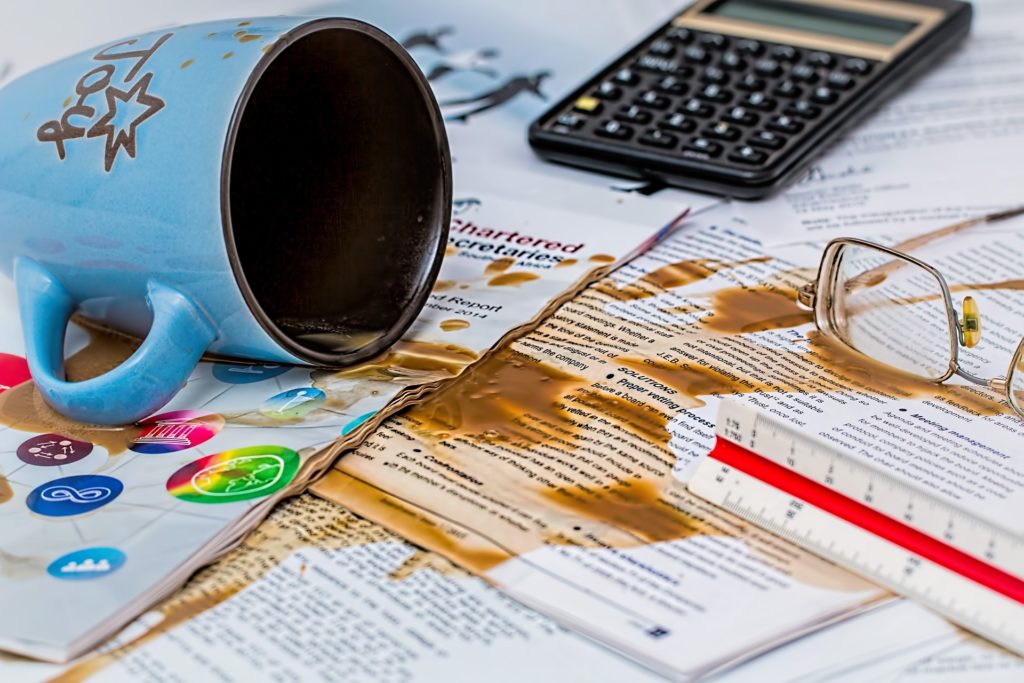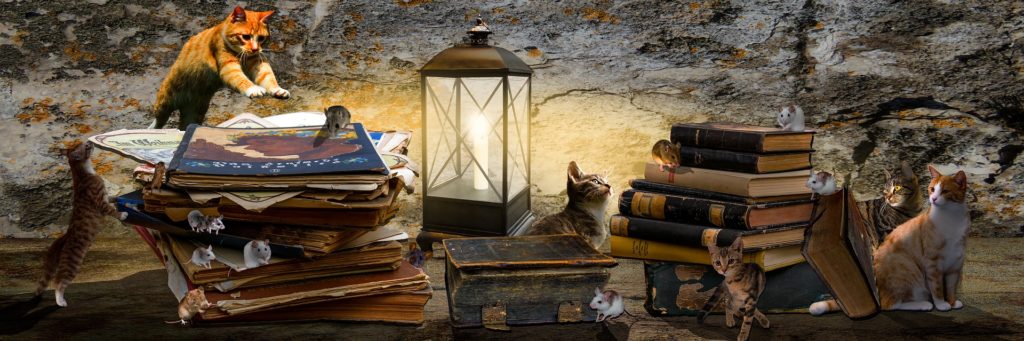前回、前々回と家賃の値上げについては必ずしも従わなくても良いという話をしました。また、家賃の話し合いに折り合いがつかない場合には供託という方法があることにも触れました。今回は値上げ拒否の具体的な方法などについて書いてみたいと思います。
家賃の値上げ連絡が来た!応じられない場合どうしたら良い?
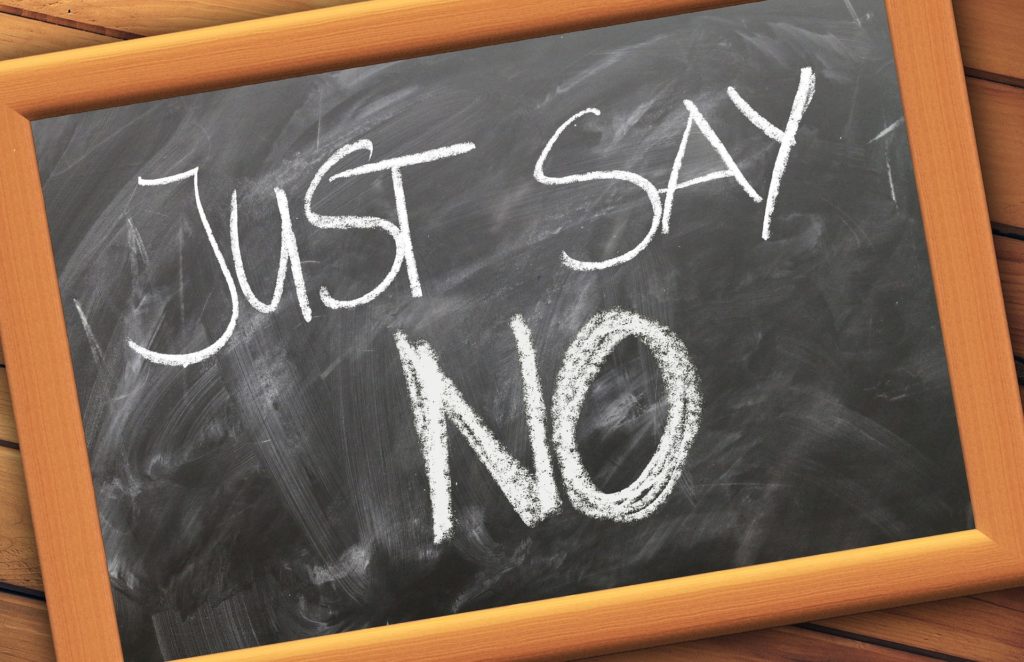
前回、前々回のブログを読んで頂いた方であれば、大家さんや管理会社から家賃を値上げしたい、と通知が来ても、冷静に対処することができるかも知れません。では、具体的にはどうやって断れば良いでしょう。もちろん普段から大家さんとまめに連絡を取っていて、直接断れる方は問題ありません。もっともそんな方には不意打ちのような値上げ通知を送られたりはしないと思います。
値上げ通知が届いたら、まずはどこから届いたか確認しましょう。大家さんが直接来ているのか、管理会社を通しているのか。管理会社を通しているなら管理会社に連絡するのが筋です。
差出人を確認したら電話か、或いは手紙で、値上げには応じられない旨を通知しましょう。注意すべきは、大家さんにも事情があって値上げしてきている、ということ。いくら双方の合意がなければ値上げすることができないからといって、居丈高に「値上げになんて応じられません!」とけんか腰に回答したら、関係はこじれるだけです。丁寧に値上げには応じられないこと、そして値上げの事情を尋ねて下さい。
そもそも値上げってできるの?

では、家賃の値上げはどういうときに出来るのでしょう。基本的には契約書の定めに拠るのですが、一般的に1.土地や建物の価格が上がることによって大家さんの負担する租税等が増加したとき。2.経済状況の変化によって現在の家賃が不相応となったとき。3.周辺の類似物件の家賃と比べて不相応となったとき。に家賃の値上げが認められると言われています。また値上げのタイミングは更新など再契約をするときに限られません。原則としてはいつでもすることが出来るのです。もっとも、更新などのタイミングのほうが話を切り出しやすいので、更新のタイミングに値上げの連絡をする、ということが多いようです。
先ほど書いたように値上げの事情を尋ねると、おそらく上記の項目に該当するような回答があると思います。これに関する資料を求めて検討する、場合によっては納得のいく範囲で値上げに応じる姿勢を示すことも大家さんや管理会社と友好な関係を築く上で必要なことだと思います。
ところで更新料って払わないといけないの?

値上げの通知が来るのは更新のタイミングが多いと書きましたが、じゃあ更新料は払わないといけないの?これも双方が合意しなければ払う必要がないんじゃないか、とお思いになる方もいらっしゃるかも知れません。まさにそのとおり!法律で定められた支払義務のある費用ではありませんので「双方が合意」しなければ払う必要はありません!
ただ、注意して下さい。あなたはそのお部屋に入居する際、更新料の定めのある契約書にサインして(合意して)賃貸借契約を結んだはずです。そう、「双方の合意」は既にあるのです。
近年、不当に高い更新料の設定については消費者保護の観点から無効の判決が出たと報道されたこともあり、「更新料は払わなくても良い」と思っていらっしゃる方もいるかも知れませんが、1年又は2年毎の更新につき2ヶ月分程度の更新料であれば「特に高額とは言えない」として有効であるとする最高裁判例が出ていることもあり、原則としては支払う必要があるのです。
更新料を支払いたくない場合は、更新料の設定のないお部屋を探すしかありません。ただし、更新料は家賃の補充、前払的性質を持つとされています。更新料のないお部屋はその分家賃が高くなる傾向がありますので、ご留意下さい。
以上、今回は、家賃の値上通知に対する対応と更新料について書いてみました。
大家さんや管理会社とは友好的な関係を築く方が気持ちよく住まうことが出来ると思いますので、出来るだけ平穏な話し合いをおすすめします。しかし、執拗な家賃の値上要求や不当に高額な更新料にお悩みでしたら、ぜひ専門家(弁護士)に相談してみてください。色々アドバイスして貰えると思いますよ。